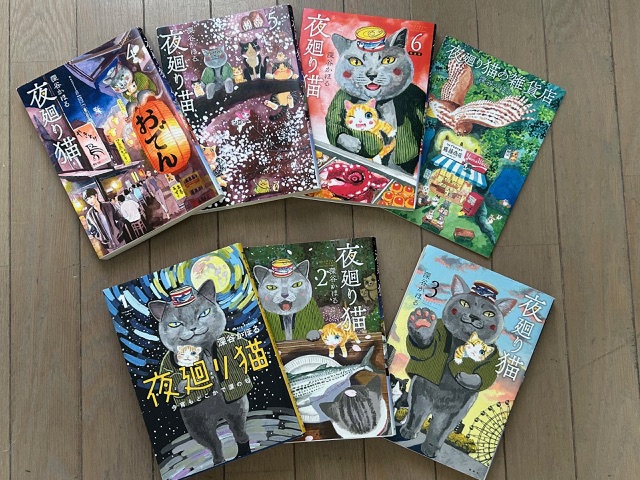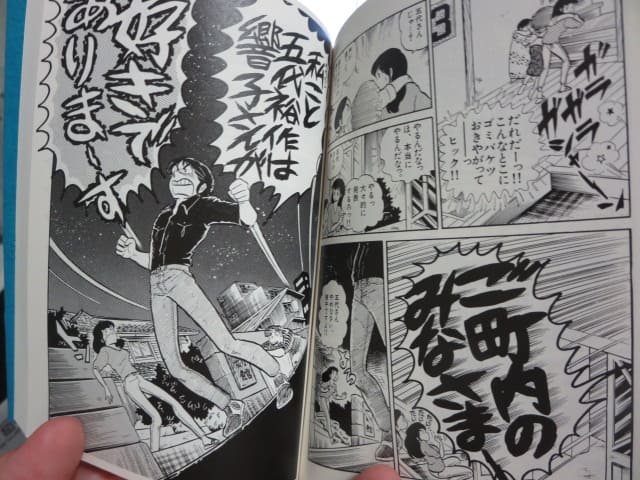SFマニアの私が解説する世界的ヒット作「三体」の魅力
偏愛・脳汁を語るサイト「ヲトナ基地」では、多数の「愛しすぎておかしくなるほどの記事」をご紹介してまいります。 ヲトナ基地で今回紹介する記事は「ドラマに小説に大盛りあがりの中国SF『三体』の魅力を語る!」。冬木糸一さんが書かれたこの記事では、中国SF『三体』への偏愛を語っていただきました!
こんにちは、冬木糸一です。
今回は日本を含む世界中でベストセラーとなり累計で3000万部以上を売り上げた歴史的な中国SF『三体』を、今日本で読むことができる小説と二本のドラマを中心に紹介させてもらおうかと思う。というのも、『三体』は先日三部作のすべてが文庫化され、別作者によるスピンオフ長篇『三体X』や事実上の前日譚『三体0』も翻訳済み。さらにはNetflixで第一部のドラマ化、中国本国で作られたドラマ版も各種配信サイトで視聴できて──と、小説から映像媒体まで入口が揃ってきたからだ。
『三体』とは何なのか? なぜ世界中で盛り上がっているのか?
最初に『三体』の盛り上がりについて触れておくと、これが世界的に人気を博したのは、世界的に有名なSF賞であるヒューゴー賞を、2015年にアジア人作家として初めて受賞したのがきっかけとなっている。その受賞後、オバマ元大統領、FacebookCEOのマーク・ザッカーバーグなどの著名人も相次いで推薦。もともと中国国内では盛り上がっていた作品だが、その人気が世界中に広がっていったのだ。
日本でもこの時期(2015年頃)以降に「三体っていうのがスゴいらしい」「いつ日本語に翻訳されるんだ!」「原書・英語で読んだけどすごかった!」と評判が伝わってきたものだ。そこから日本で第一部が翻訳で読めるようになったのが2019年のこと。その後あれよあれよという間に日本でも累計80万部を突破し、今年はついにドラマも日本で公開され──と、いまだに破竹の勢いでその人気が広まっているのだ。こうした人気には中国が国策としてSFを推進していることも関係している。なかでも成都は「SF都市」としてPRされ、昨年は中国で初の世界SF大会(世界SF協会が主催し、戦術のヒューゴー賞の受賞作を参加者らの投票で決定する)もここで開催された。
入口は多く、そのどれもに良さがあるので、『三体』未体験、もしくは観ていない・読んでいないものがある人は、本記事が手をつけるきっかけになったら幸いである。
原作《三体》三部作
というわけで、最初にすべての基本となる原作小説の紹介から入ろう。現在三部作すべてが文庫化されており、第一部は一冊、第二部『黒暗森林』と第三部『死神永生』がともに上下巻となっている。これまで内容の話を一切せずに持ち上げてきたが、本作の物語は基本的にはシンプルな”ファーストコンタクト物”であるといえる。
ファーストコンタクト物とは人類が地球外文明・生物とはじめて接触した時の驚きやコミュニケーション、時には戦争に至るまでを描き出すSF内のサブジャンルだ。《三体》三部作の中で、人類ははじめて地球外の生命体と遭遇し、種の存続を賭けて戦うことになる。本作が世界中で評価されたのは「それだけのことをどこまでもスケールをデカく、しかも緻密に突き詰めて描き出したから」という点にあるだろう。
さらには、中国発の作品らしく中国の文化に根ざした──本作は文革の過程で科学者の父を殺され、人類に絶望した女性が最初の主人公となる──第一部から、次第に地球人類全体の物語へと移行し(第二部)、最終的にはこの宇宙に住まう生命全体の行く末を描き出す(第三部)ような、ローカルな文化描写とグローバルを超えた宇宙論的な視点を併せ持っている点も、世界中で大ヒットしている要因といえる。
その性質上物語は第一部〜第三部まででテイストが異なっていて、筆者(冬木)は四回ほど読書会に参加したがみんな好きな部もバラけていた。たとえば第一部はすべてのはじまりを描き出す物語で、なぜ地球から遠く離れた地に住んでいた三体星人が地球を発見したのか、またなぜ地球人類を征服するためにやってくることになったのか、その顛末が中国での文化大革命と合わせて描き出されていく。1970年代から2000年代の比較的現代に近い時代を描いていて、文学的な魅力が光るパートだ。
続く第二部は、地球に向かってくる三体星人をどうにかして打ち倒さねばならぬ──となった地球人類が、三体星人よりもはるかに劣る科学技術で奮闘する「頭脳バトルパート」にあたる。この部数がエンタメ的な濃度は一番高い。というのも、ある事情から地球の通信はすべて三体星人に傍受されていて、声に出したり通信を行うとすべてバレることから、信頼できるのは「天才の頭の中だけ」という状態から頭脳戦がはじまるのだ。三体星人に対抗するため作られた惑星防衛理事会は「面壁計画」を立ち上げ、天才的な四人の人物を選出し、彼らに人類のリソースを集約することになる。
面壁者と呼ばれる選ばれし四人は、そのリソースを真意を説明せずともあらゆることに使用することができる。一見不可解なことや馬鹿げたことにリソースを費やしているように見えても、それはすべて人類もろとも三体星人を騙すための”ブラフ”なのかもしれないのだ。
それに続く第三部はこれまでの二作と比べるともっともSF度の高い作品だ。物語はまず第二部で進行していた事態の裏側で起こっていたことから始まり、最終的には惑星規模を超えて全宇宙における生命の生存戦略にまで話のスケールが及ぶ。
著者の劉慈欣によれば、最初の二巻はSFファン以外の一般読者に広く受け入れてもらうために、現代や近未来を舞台にし、物語の現実感を高めた。しかし第三部に至っては、物語ははるかな未来や本格的に宇宙を舞台にした物語となり、ハードコアなSFファンを自認する劉慈欣自身が心地よく感じる、”純粋な”SF小説を書くようにしたのだという。そうした振り切った作品として書かれた第三部はしかし中国本国でも大人気となり、本邦での三部の評判も(普段あまりSFを読まない読者にも)良い。
読み始めた読者には、ぜひ第三部のラスト──壮大な物語の果てに、寂寥感の残る情景が訪れる──にたどり着いてもらいたいものだ。
ドラマはどちらから見るべきか?
続いて映像作品の紹介に移ろう。こちらは現在日本国内から視聴できるものとしては、Netflix版とテンセント版の二種類が存在する。それぞれの特徴を書いておくと、Netflix版は主な舞台をイギリスに移して原作を再構成した物語になっていて、話数的にも概ね原作第一部に相当する部分が全八話とコンパクトにまとまっている。
もう一方のテンセント版(現在AmazonPrimeやU-NEXT、FODプレミアム、TELASAなどに有料登録することで視聴可能)は本家本元の中国で作られたドラマだ。中国人中心のキャストで、各話40〜50分の全30話と、たっぷりと尺を使って原作に忠実に映像化を試みているのが特徴である。
Netflix版について
原作の再現度や、「文字はたくさん読む気がしないけれど物語は原作通りのものが堪能したいな〜」というのであればテンセント版を薦めるが、Netflix版にはNetflix版の良さもある。そもそもNetflix版は最初から制作を進めるにあたって大きな制約があったようで、制作者らは「ドラマを英語版として作る」権利を持っており、登場人物はみな英語で話すことを前提として作品を作らなければならなかったのだ。
それで改変して物語がとんちんかんだったら問題だが、本作は原作既読勢からみてもそう違和感のない内容に仕上がっている。違和感なく物語を再構成するため、物語の舞台は中国からイギリス・オックスフォードへと移り、さらに各部にまたがった物語を一貫した(人間関係の)ドラマとしてまとめあげるために、原作で第一部、第二部、第三部で異なるはずの登場人物を序盤から登場させたり──と、さまざまな変更を行っている。
本作のスタッフは大きく話題になったファンタジー大作ドラマの『ゲーム・オブ・スローンズ』と共通していて、彼らが経験豊富で得意な群像劇の魅力を本作で存分に発揮しているといえるだろう。後述するが、テンセント版では原作で重要な意味を成す文化大革命のシーンが大幅にカットされている一方、このNetflix版では冒頭から(文革のシーンを)丹念に描くなど、プロットや登場人物は異なっても作品の核はきちんと引き継いでいる。「もう一つの三体」が楽しめるのは間違いなくNetflix版の美点だ。
登場人物がわっと出てくることもあって序盤のテンポこそ悪いものの、後半の山場である「古筝作戦」(第五話「審判の日」)まで視聴すれば、あとはラストまで一気だろう。
テンセント版について
一方のテンセント版の良さはなんといっても長大な尺を活かした映像表現の豊かさだ。たとえば、原作『三体』の第一部では、VRゲーム「三体」が重要な役割を果たすが、VRというだけあって視覚的にはなんでもあり。たとえば十万桁までの円周率を求めよという始皇帝の無茶振りに答えるため数百万の軍隊を用いて人間計算機を構築するシーンが原作にはあるのだが、こうした壮大なシーンも予算も尺もとってじっくりと描き出している。
他にも原作勢的には、原作でちょい役だった人たちがこのドラマ版では30話と尺たっぷりなせいか描写が盛られていること(史強の部下である徐冰冰など)、原作通り物理学や天文学の専門用語が飛び交うこと──といったあたりは、『三体』の物理学部分の壮大なホラの吹き方が好きな人にはたまらないだろう。役者陣も、中心人物の汪淼を演じる张鲁一をはじめとして、個人的には非常によくマッチしていると感じた。
全30話と長大なドラマで説明がひたすら長い回などもあるのでダレがちだったり、こちらはやはり文化大革命の描写が弱い点、主人公らを明確な悪にしづらい点(先述の「古筝作戦」の描写でそれが露骨に出る)もあり、良い点、悪い点がNetflix版とテンセント版では見事に表裏に分かれているなと感じる。
おわりに
原作やドラマなど、何から『三体』に入るのが正解ということはないので、この記事で興味を持った人は(まだ読んで/観ていないものがある人も)手を出すきっかけになってもらえたら嬉しい。このあとドラマもシーズンが続いていくし、映画化も、スピンオフ作品も出てくるようなので、しばらく『三体』フィーバーは続きそうだ。