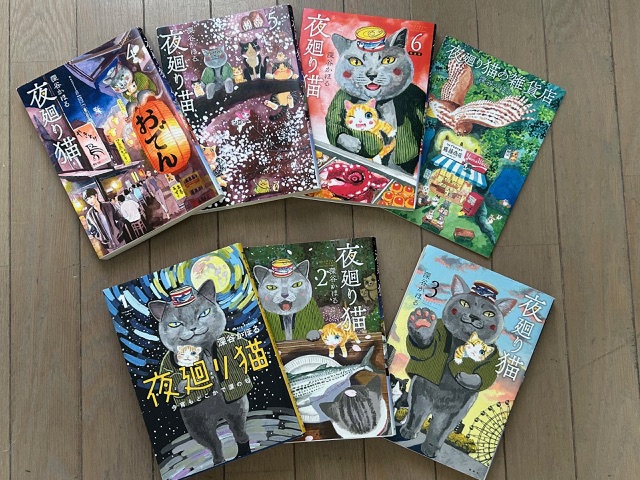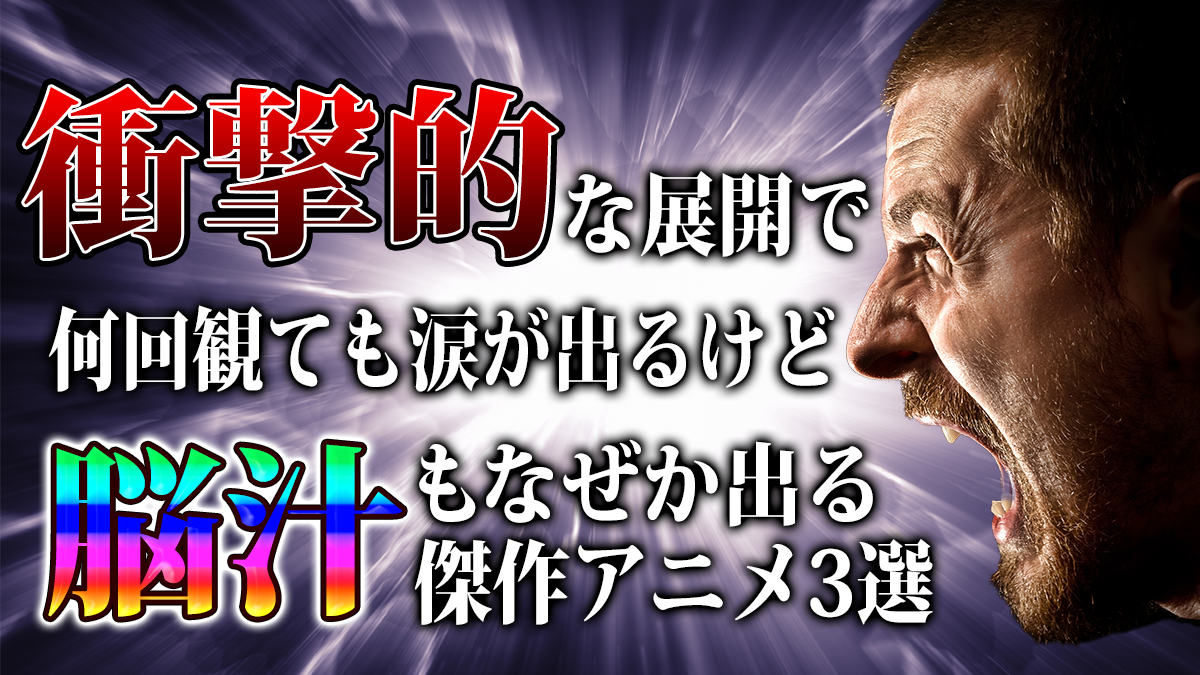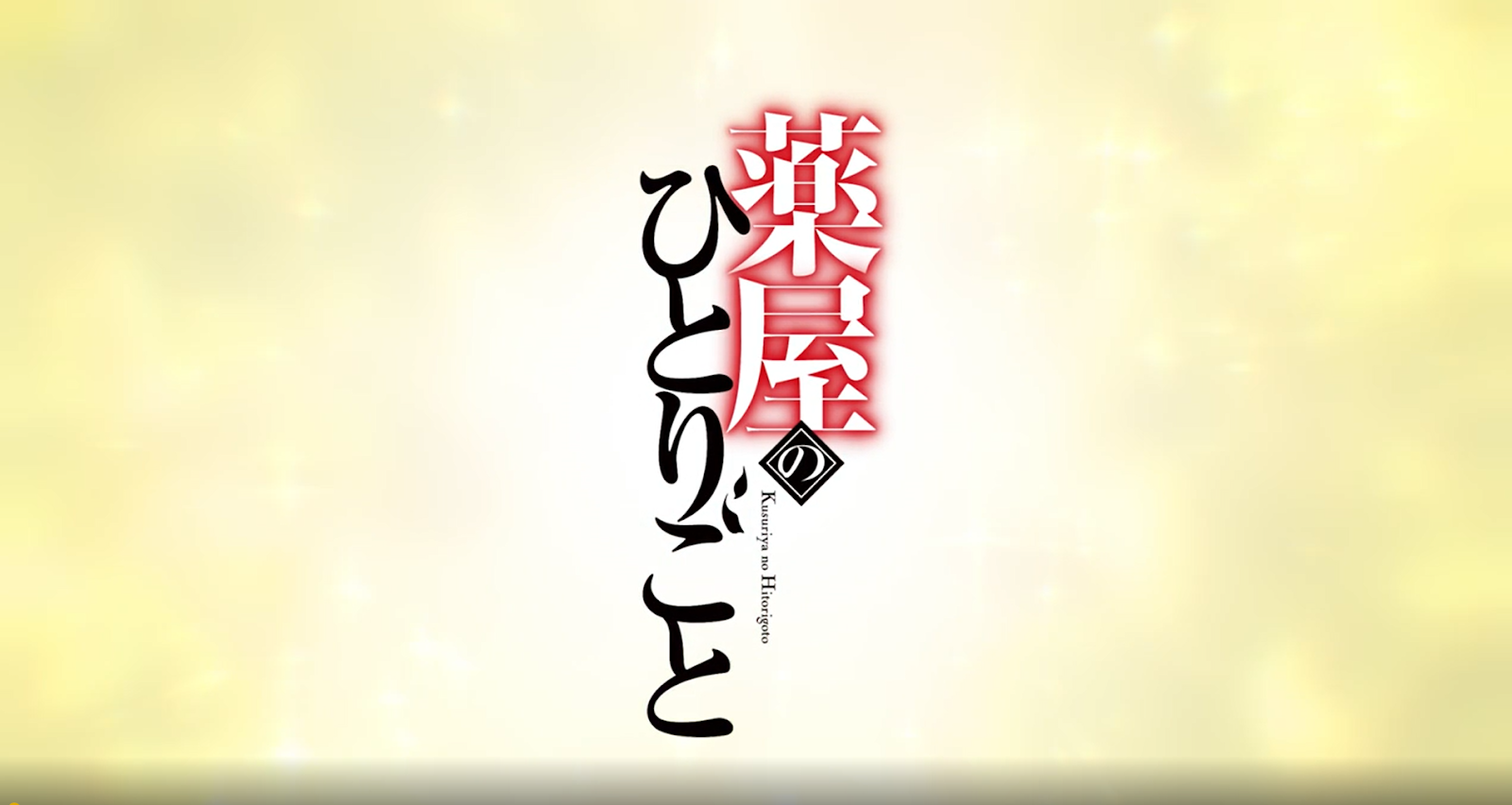衝撃的な展開で何回観ても涙が出るけど、なぜか脳汁も出る傑作アニメ3選
偏愛・脳汁を語るサイト「ヲトナ基地」では、多数の「愛しすぎておかしくなるほどの記事」をご紹介してまいります。 今回は、あまりの衝撃的な展開に、何度観ても号泣してしまうアニメを厳選してご紹介!筋金入りのアニメファンであり、スロットを愛して止まない放蕩ラザイエフさんがまとめてくれたようですが…?
はじめまして!大学在学時より、周囲の友人やライターをパチスロの世界に誘うことをライフワークとしております放蕩ラザイエフ(@prodigalrzhyev)と申します。
今回は「展開が衝撃的で何度観ても脳汁が出てしまう」いや失礼、「展開が衝撃的で何度観ても泣いてしまうんだけど、なぜか脳汁が出ているような気がしてならないアニメ」をご紹介したいと思います。
なお、読者の皆様が作品を深く理解していただけますよう、作品が公開された際に社会に与えたインパクトや、当時展開された批評・考察についても紹介するつもりでおります。ネタバレもございますので作品未視聴の方はご注意ください。
ちなみに、この記事では号泣必至のエピソードを選り抜いてご紹介していますし、私自身、映像を観返すたびに登場人物たちの覚悟や行動、そしてその悲劇的な結末に涙しているのですが、
どういうわけか、それぞれのシーンで惹き起こされる「悲しみ」の感情は、「喜び」の感情とも強く結びついている気がしてならないのです。
人間の感情って、不思議ですね。それではさっそく作品を振り返っていきましょう!
「つまり記憶と言うものは決してそれ単体で存在せず、それを取り巻く環境に支配されているという訳だ」 - 『交響詩篇エウレカセブン』ストナー
1.「魔法少女まどか☆マギカ」(2011年公開)
1話「episode1 夢の中で逢った、ような……」はABEMAにて無料視聴可能。
出典:ABEMA「魔法少女まどか☆マギカ」(https://abema.tv/video/episode/26-1csgwzchpyj_s1_p1)
■あらすじ見滝原中学校で平和な日々を過ごす中学2年生、鹿目まどか。ある日、転校生として同じクラスにやってきた謎の少女・暁美ほむらが、マスコットのような可愛らしい見た目の生き物「キュゥべえ」を襲撃している場面に遭遇する。怪我をしたキュゥべえを助ける途中、友人である同級生の美樹さやかとともに摩訶不思議な空間に迷い込んでしまうも、学校の先輩であり"魔法少女"である巴マミの助けによって脱出に成功。マミに治療を受けたキュゥべえは、「ぼく、君たちにお願いがあって来たんだ」と笑顔で二人に語りかける。「僕と契約して、魔法少女になってほしいんだ」
ポイント(1)『現代用語の基礎知識』にも掲載された「マミる」
脚本を担当したのは、のちに『Fate/Grand Order』を手掛ける虚淵玄。漫画家・蒼樹うめ(通称「うめてんてー」)原案の、かわいらしくほのぼのとしたタッチのキャラクターが、ダークで重厚な展開に翻弄される姿が注目を集めました。
https://twitter.com/madoka_magica/status/1879128830440272124?ref_src=twsrc%5Etfw
↑物語の鍵を握るマスコット"らしきもの"「キュゥべえ」。このアニメ随一の外道ですが外見は本当に可愛らしいですね。
本作を語るうえで外せないのが、第3話 「もう何も恐くない」で発生した巴マミの戦死、通称「マミる」。主人公の先輩である魔法少女・巴マミが、敵である"お菓子の魔女"に頭を丸かじりされ、物語から早々に退場したことに視聴者は騒然。
https://twitter.com/madoka_magica/status/1879143738775384330
▼3話はこちらで公開されています。
https://www.nicovideo.jp/watch/so13395169
「魔法少女モノでキャラが戦死する」想定外の展開が話題を呼び、当時ネット配信していたニコニコ動画では3話から急激に再生数が増えました。
当初は"日常系の、ほのぼの学園アニメ"だと思われていたものが、このエピソード以降はハードな作風に変化。魔法少女たちがその決意を挫かれ、精神的に追い詰められていく様子が描かれます。
なお、この回を機に、他のアニメでもキャラクターの頭部が消失するような退場をした際に「マミる」「マミった」と呼ぶ人が増加。用語として確立したことから『現代用語の基礎知識 2012年版』に「悲惨な死に方をする」という定義で掲載されました。
■参考:マミる (まみる)とは【ピクシブ百科事典】
マミる 『魔法少女まどか☆マギカ』関連の用語。※この記事はグロテスクな要素があります。閲覧の際はご注意ください。 dic.pixiv.net
ちなみに遊技機ですと、第3話のタイトルでもあり、後世に語り継がれる死亡フラグともなった「もう何も恐くない」という巴マミのセリフが、多くの人の脳汁が出るトリガーになっているとかいないとか。
実際、マミさんには申し訳ありませんが私は出ます。なぜならART中に突如出現するPUSHボタンを押すと表示されることがあったから(恩恵は大抵、レア役+ゲーム数上乗せ)。
↑2019年10月30日に筆者撮影。パチスロ「まどか☆マギカ2」ではマミさんの死亡フラグ「もう何も恐くない」がちょい熱めの演出として使われていた。
ポイント(2)平成ライダーシリーズ『仮面ライダー龍騎』と展開が酷似!
平成仮面ライダーシリーズの3作目『仮面ライダー龍騎(2002年)』と物語の展開が相似していることにも注目ポイント。同作のキャッチコピーは『戦わなければ、生き残れない』。鏡の中のモンスターと戦いつつ、並行してライダー同士が自らの願いをかなえるために「それぞれの立場の正義」を掲げてバトルロイヤルを行う異色の作品です。
https://www.youtube.com/watch?v=d39Mm_2TkUA
『魔法少女まどか☆マギカ』は、既に多くの人が指摘している通り・登場人物同士が戦い合うこと・仲間たちが悲惨な死を遂げること・物語の鍵を握る人物がタイムリープ能力を持っていることなど、『仮面ライダー龍騎』のシナリオをそのまま落とし込んだかのように共通点が多い作品でもあります。ルーツとなった作品と表現しても良いかもしれません。
なお、龍騎とまどマギで決定的に異なる点はタイムリープ能力がより残酷な使われ方をしていること。第10話「もう誰にも頼らない」では、転校生・暁美ほむらがとある理由からタイムリープを何度も繰り返していたことが判明します。
出典:X|@saidforest02
▼10話はこちらで公開されています。https://www.nicovideo.jp/watch/so13866019
時間を止める能力を駆使して、様々な施設から火器を調達することにより本作のラスボスである「ワルプルギスの夜」に繰り返し挑むほむら。しかしながら作中最強の魔女に敵うことはありません。
状況があまりに凄惨過ぎて、視聴者ともども「嫌だぁ…もう嫌だよぉ…こんなの…」となっているところに突如挿入される特殊エンディング。10話をリアルタイムで視聴していた自分は、心の底から納得した一方で「人の心とかないんか?」と思いました。
https://www.youtube.com/watch?v=XCGk9nWx6DE
なお、ほむらのタイムリープにまつわるエピソードは、遊技機においてはいわゆるロングフリーズ(※1)や特化ゾーン(※2)と絡められることが多いため、打ち手は10話・11話を観ているとなぜか脳汁が出がちです。
※1 ロングフリーズ…パチスロにおいて、特別な条件下で発生するプレミア演出。発生した際の恩恵は大きく、多くの機種で大量の出玉を獲得しやすい状態になる。演出には往々にして作品の最も感動的なシーンが選ばれがち。※2 特化ゾーン…パチスロにおいてAT・ARTのゲーム数や獲得枚数を引き上げるゾーン。大抵の機種において「その日一番の叩きどころ」となり、特に「まどか☆マギカ」シリーズでは最もハラハラする楽しい時間になりがち。
私ですか?『初まど』『まどマギ2』ともにロングフリーズは引けずに終わりましたが、引いた時の映像は見たことがあるから脳汁は出ますね。自分は「私はまどかとは 違う時間を生きてるんだもの!」というほむらのセリフのあとに、画面がホワイトアウトしてタイトルロゴ+赤7同色BIG(単独)のナビが出てくる様子(発生確率:約1/131,072)を思い浮かべますが、皆さんはそうじゃないんですか?
https://www.youtube.com/watch?v=skY9DCAnaI8
ポイント(3)本当に"神回"と化した最終話「わたしの、最高の友達」
10話「 もう誰にも頼らない」、11話「最後に残った道しるべ」も驚愕の展開でしたが、最終話「わたしの、最高の友達」も最高でした。ポイントは「自己犠牲の精神」です。
アルティメットまどか 私の願いは、全ての魔女を消し去ること… 大ヒットアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の最終回にて、主人公「鹿目まどか」 www.goodsmile.info
詳細はアニメ本編or遊技機の演出をご覧ください。何度観ても涙が出るのはアニメ本編の方で、何度見ても脳汁が出るのは遊技機の方です。
ほむらによる度重なるタイムリープが遠因となり、潜在的に途方もない資質≒宇宙を延命させるための莫大なエネルギーを内包することになった鹿目まどか。最終話にて、その資質を逆手に取ることにより"ある願い"を成就させます。
その願いとは「全ての宇宙、過去と未来の全ての魔女を、まどか自身の手で生まれる前に消し去ること」。
自信の魂を対価にするとはいえ、"新しい法則"を生成するという途方もない願いに対して「魔法少女になってほしい」と勧誘し続けてきたキュゥべえは驚愕します。「その祈りは…そんな祈りが叶うとすれば、それは時間干渉なんてレベルじゃない!因果律そのものに対する反逆だ!」
この願いが叶えば、まどかは個体として完全に消滅し、「未来永劫に終わりなく、魔女を滅ぼす概念として宇宙に固定される」ことになります。
まどかの願いを再確認するキュゥべえ。「君は本当に、神になるつもりかい…?」
キュゥべえの問いかけに答えるまどか。「神様でも何でもいい。今日まで魔女と戦ってきた皆を、希望を信じた魔法少女を、私は泣かせたくない。最後まで笑顔でいてほしい。それを邪魔するルールなんて、壊してみせる。変えてみせる」「これは私の祈り。私の願い。…さあ、叶えてよ、インキュベーター!!」
出典:X|@shibahuleaf
▼最終話はこちらで公開されています。https://www.nicovideo.jp/watch/so14227682
改めて最終話を観返すと、まどかの覚悟が決まり過ぎており、外面を作れないくらいダラダラと泣いてしまいます。逆に、遊技機の方でこのシーンを見かけると「すでに大体とんでもないことになっている」ためダラダラと脳汁が出続けます。
かなり感動的なシーンのはずなんですけど、遊技機の性質上、ロングフリーズや有利区間完走とは切っても切れない関係性にあるんですよね。なんというか、自分で書いていてちょっと悲しいです。
https://www.youtube.com/watch?v=yQ1zzQxC17Y
2.「コードギアス 反逆のルルーシュ」(1期:2006年、2期:2008年)
https://www.youtube.com/watch?v=yLvlQPLAors
■あらすじ神聖ブリタニア帝国に支配された日本で、目と脚が不自由な妹ナナリーと暮らすブリタニアの元皇子ルルーシュ・ランペルージ。ある日、テロ活動に巻き込まれた際に出逢った謎の少女・C.C.(シーツー)により、他人に自分の命令を強制できる絶対遵守の力「ギアス」を授けられる。妹のナナリーが安心して暮らせる場所を作るため、仮面で素顔を隠して「ゼロ」と名乗り活動を開始するルルーシュ。レジスタンス組織「黒の騎士団」を結成し、ギアスを駆使してブリタニア帝国に対し戦いを挑む。「撃っていいのは、撃たれる覚悟がある奴だけだ!」
ポイント(1)人呼んで"厨二病大量製造"アニメ
特殊能力で社会をどうこうしようとする作品群としては『DEATH NOTE』と双璧をなすと思います。
「あなたがもし、ずば抜けて頭が良くて、"他者に何かを強いる能力"があったらどうする?」という中学生の頃に妄想しがちなIFシチュエーションを描きつくした"厨二病製造アニメ"と言っても過言ではないでしょう。
https://www.youtube.com/watch?v=68uCzPOWvcE
なお地上波で放送されていたのは2006〜2008年で、私が高校生の頃でした。作品を観たのは成人してからですが、正直「リアルタイムで観ていなくて本当に良かった…」と思います。「今の自分は冴えないけど、ルルーシュみたいに普段は仮面を被っているだけなんですよね」みたいな自意識が芽生えたら大変なことになっていた気がする。
ちなみに遊技機の話に移ると、自分は『初代』は打っていませんが『R2』と『3』は打ち込みました。これはコードギアスが好きな人あるあるですが「(パチンコ・パチスロを)打っていいのは、撃たれる覚悟がある奴だけだ」って言いがちです。愉快愉快。
https://www.youtube.com/watch?v=0peGXuCuGZc
ポイント(2)怒涛の早さで物語が展開するグルーブ感
一話で何回山場が来た???と確認したくなるくらい、怒涛の速さで物語が進むことも本作の見どころです。「幼馴染であり一番の親友が、実は敵陣営のエースパイロットだった」「自身が手にした特殊能力(ギアス)の暴走により、初恋の相手を自ら殺害する羽目になる」「裏切りに次ぐ裏切りにより、果ては国際社会そのものと対立する」など、1期・2期ともに衝撃的な展開がひたすら続きます。
個人的に一番キツかったのは、幼馴染である枢木スザクと完全に対立する原因となった「ユフィの死(通称:血染めのユフィ)」です。
https://www.youtube.com/watch?v=BwzHwItC4XI
私自身、視聴した当時はすでに大学を出ていたのにも関わらず、ユフィがスザクに向けた遺言「学校…行ってね…」が深く胸に刺さりました。その生まれや能力ゆえに、主要人物たちがあまり学校に通えていないことも『コードギアス』の特徴なのですが、『呪術廻戦』の五条先生が言う通りで、若人から青春を取り上げるなんて許されていないと思うんですよね。
ちなみにパチスロでは、出玉が絶好調な時にこのシーンが飛んでくることがあるのですが、エピソードボーナス(※3)で『血染めのユフィ』を引いてしまった時は正直うっすら泣いています。
※3 エピソードボーナス…通常のボーナスと異なり、なんらかの恩恵が付いてくる特殊なボーナス(ATやARTが確定する、設定が示唆または確定されるetc)。やはり感動的なシーンが演出に選ばれがち。
俺、あまり真面目に学校に通ってなかったな…。なんだろう、作品を反芻するためにパチスロを打っているところはあるんですけど、このシーンだけは脳汁を出すのが申し訳なく感じるので、何度も見せるの止めてもらっても良いですか?
ポイント(3)衝撃のラスト!「ゼロレクイエム」を見逃すな
物語後半、実兄であるシュナイゼルの策略により「絶対遵守のギアス」という強力な能力を保有していることが明らかにされたことで、ルルーシュはこれまで率いてきたレジスタンス組織「黒の騎士団」とも敵対することになります。
しかし逃走の果てに、父である第98代皇帝・シャルル・ジ・ブリタニアを世界から消滅させることに成功。そこから1か月後、ブリタニア帝国を追放されたはずのルルーシュが、なんと第99代ブリタニア皇帝の座に就きます。
https://www.youtube.com/watch?v=79G5OA_kdCc
世界を手中に収める計画「ゼロレクイエム」を完遂させるべく、かつて敵対した幼馴染・枢木スザクおよびその側近数名と動き始めるルルーシュたち。ついに、兄のシュナイゼルが率いる神聖ブリタニア帝国軍と、自身がこれまで率いてきたレジスタンス組織「黒の騎士団」までをも敵に回します。
そしてこの先には、人々にギアスをかけた代償として涙なしには見られない結末が待ち構えているのですが、こちらもパチンコ・パチスロでは大当たり演出と絡んでいることが非常に多いため、打ち手は映像を観るとなぜか脳汁が出がちです。悲しすぎる。
それでも、我々は忘れてはいけないのです。「撃って(打って)いいのは、撃たれる覚悟がある奴だけだ」と…。
https://www.youtube.com/shorts/AYNAseiTn_o
3.「甲鉄城のカバネリ」(2016年)
https://www.youtube.com/watch?v=NljBw9RtOx4
■あらすじ蒸気機関が発達した極東の島国・日ノ本(ひのもと)を舞台に、装甲車両のような蒸気機関車「甲鉄城」の乗客員と、不死の怪物「カバネ」との戦いを描いたスチームパンク。ウイルスによって増殖する不死の怪物「カバネ」の驚異に対抗すべく独自に武器を開発していた青年・生駒は、ある日自らの居住区に侵入してきたカバネに噛まれてしまう。自ら開発した装置によってウイルス感染を防ぎ、奇跡的に一命を取り留めた生駒。「甲鉄城」に乗り込んで居住区脱出を試みるも、噛み傷を乗員に見られたことにより感染者と認定され、搭乗員から攻撃を受けて強制的に下車させられる。駅に取り残されて打ちひしがれる生駒の前に、一人の少女(無名)が甲鉄城から降り立った。友人である逞生(たくみ)の助けもあり、甲板に引きずりあげられた生駒。自刃を迫る搭乗員たちに対して、驚異的な身体能力を誇る無名が自らの秘密を明かす。「私たちはカバネリ。人とカバネの狭間にある者」
※補足※このアニメが用いられたスロットマシンの登場により、「どっこいしょ」の語源である言葉『六根清浄』が、脳汁が大量に出る魔法の言葉に変化してしまったことはあまりにも有名。
https://www.youtube.com/watch?v=2b8SvG0LRhk
ポイント(1)This is クールジャパン!アニメーションの進化形態がここにある
制作は『進撃の巨人』を手がけたWIT STUDIO。『進撃の巨人』といえば立体機動装置のワイヤーアクションシーンがとんでもなく動いたことが記憶に新しいですが、『甲鉄城のカバネリ』もカバネとの殺陣を中心に負けず劣らずの動きっぷりで洗練されたアニメーションをお楽しみいただけます。
たしか2012年頃までは「作画崩壊」が話題になるアニメが時々出現した記憶があったのですが、2016年公開の『甲鉄城のカバネリ』については崩壊の「ほ」の字も見えないくらい、素人目に観てアニメーションが強烈な進化を遂げています。
どちらかといえば公開時点で話題になっていた記憶はそれほどなく、2022年のパチスロ導入から急激に話題になり始めた印象がある本作ですが、少なくとも最近アニメをあまり観ていない人は「2016年時点でアニメーションってここまで進化してたんだ!?」と驚くこと必至かと思います。
これはもう遊技機とか関係なく、普通に映像作品としての質が凄くて脳汁が出ます。
ポイント(2)『コードギアス 反逆のルルーシュ』とテーマが一緒!?
また、本作を観る前に予備知識として押さえておいてほしいのが、シリーズの構成・脚本を担当しているのが先ほどご紹介した『コードギアス 反逆のルルーシュ』と同じ大河内一楼氏である点です。
https://twitter.com/NetflixJP_Anime/status/997020208844832768?ref_src=twsrc%5Etfw
アニメ作品として、高速で移動する甲鉄城で行われるカバネとの戦闘シーンはたしかに魅力的ではあるのですが、物語のテーマとして「コードギアス」と同じく「父殺し」や「革命(※こちらは倒幕)」が通底している点も見逃せません。 なお『コードギアス』ではルルーシュによる"父殺し"は全50話の間に1回のみで済みましたが、こちらは12話の中で計2度成し遂げられました。正確には、"父殺しの後に生まれた父権主義(パターナリズム)の打倒"と呼ぶのが適切かもしれません。
https://www.youtube.com/watch?v=6Uvu5nC-IMw
立場の強い者が、当事者の自己決定をよそに「こうした方がお前のためになる」として選択肢を押し付けることをパターナリズム(父権主義)と呼びますが、これを跳ねのけることは痛快ですよね。
「7話以降からやや垂れた」と言われがちな本作ではありますが、「父殺し」もしくは「パターナリズムの打破」に重点を置いた作劇であることを意識すると、より深く本作を楽しめるのではないかと思います。
ポイント(3)『水星の魔女』に受け継がれる、物語の優しい終わり方
本作で脚本を担当した大河内一楼氏は、のちに『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の脚本も手掛けることになります。
https://www.youtube.com/watch?v=eo0ZULsKMdo
『水星の魔女』は物語から離脱するキャラが控え目で良かった(と個人的には思う)のですが、『甲鉄城のカバネリ』も離脱するキャラが比較的少なかったように感じます。
大河内作品に限らず、ロボットもののアニメは自認がある人物も含めて「悪行を犯した人物は禊(みそぎ)として退場しがち」です。ただ『甲鉄城のカバネリ』では主人公勢が”ほぼ”死なずに済みます(ただし、あくまで”ほぼ”)。
また、2度目の"親殺し(パターナリズムの打破)"は、最終話にもう一人の主人公である少女・無名によって成し遂げられましたが、その際のセリフに作品のメッセージが凝縮されているように感じられました。
「私たちは、弱くても生きるよ」 「みんなで田んぼを作って、お米を食べる明日を目指すよ」「だから…ごめんね、兄様」
https://twitter.com/anime_kabaneri/status/748388117665615872
『コードギアス』において主人公のルルーシュは、ギアスの力によって他者に絶対服従を強いてきたことから、結果として自らの死で償う形でしか世界平和を実現することができませんでした。
一方で『甲鉄城のカバネリ』は、主人公たちが「カバネへの対抗策が確立されていない困難な状況の中でも、自分自身の弱さを受け入れたうえで生きていく」決断をします。
これ、『水星の魔女』の終わり方にも通ずるところがありませんか?
自身、すべての大河内作品を網羅しているわけではありませんが、少なくとも『カバネリ』と『水星の魔女』については、「親殺し」や「革命」をテーマにしたメッセージ性の強い作品を数多く手がけてきた大河内一楼氏が、視聴者に対して現実の世界とソフトに折り合い、着地するようメッセージを送った作品であると捉えています。
現実の社会で葛藤することは多々ありますけど、「自らを犠牲に!」とは考えずに「できることをするしかない」じゃないですか、結局さ。
※ちなみに脳汁の話に戻ると、私は「あらすじ」を書いた時点で出尽くしました。エピボの「明けぬ夜」で流れる『ninelie』、マジで良いよね…。
https://www.youtube.com/watch?v=j9ypaPVzrbE
■おわりに:脳汁が出る作品はまだまだあるぞ
結果的に、大河内一楼氏が携わった作品を2本紹介することになりました。「あれがない、これがない」といった問題提起はもちろん受け付けたいと思います。なぜなら記憶とは、それを取り巻く環境に左右されるものだから…。
今回は私が考える衝撃的な作品を三つ厳選してご紹介しましたが、あなただけが丁寧に語れて、それでいて脳汁が出てしまうようなアニメもまだまだ存在するはずです。たとえば『交響詩篇エウレカセブン』『バジリスク~甲賀忍法帖~』がそうですね。これらの作品については他の方に稿を譲りたいと思います。この記事でご紹介した作品を是非ご視聴いただき、皆様がいっそう脳汁を出せますよう、失礼間違えました、魂の栄養としていただけますよう心より祈念しております!!